
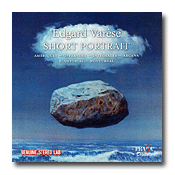
モーリス・アブラヴァネル指揮/ユタ響 (1960?1966?1968?)
Maurice Abravanel / Utah Symphony
Maurice Abravanel / Utah Symphony
Vanguard Classics / SVC-40
Praga / PRD 250 416
Praga / PRD 250 416
フィジカルメディア所有(Praga盤)。NMLはこちら。Spotifyにもあるのだが、例によってリンクを間違えており、聴けない。(…テケトーだねぇ…。😅)フランス語ウィキペディアやフィンランド語ウィキペディアによれば、これが世界初の商業録音(1960年)とのことだが、タワーレコードのPraga盤では1966年録音、discogsのCDの説明文では1968年になっている。…どれが正解なん?😅⇒Praga盤が塔で在庫ありだったので買ってみた。…ライナーノーツを読むと、演奏者と演奏場所はバラバラ(「オフランド」と「アンテグラル」はフリードリヒ・ツェルハ指揮、ウィーンでの演奏、「アルカナ」はマルティノン指揮、シカゴでの演奏、「エクアトリアル」と「ノクターナル」はアブラヴァネル指揮、ユタ大学での演奏)なのに、全部録音は「1966年」となっており、幾らなんでもちょっとオカシイ。やはり1960年が正解と思ってよいだろう。
閑話休題。…とにかくこれが世界初の商業録音であることは、まずは疑いの余地なし、だろう。(ライヴ録音、放送録音、非正規録音なら、ストコ先生あたりの海賊盤がありそうな気もするが…。)…演奏・録音だが、流石は1960年代で、マルチマイク、かつサウンドプレゼンスを無視した「超オンマイク録音」であるが、ソコが逆に「録音藝術」としての価値を高めており、正直言って、21世紀の音場を意識したワンポイントマイク録音などより、こうした「あざとい」録音の方が私は好きだ。純粋に「聴いていて面白い」。音質は「極上」であり、「…ホントにこれ、1960年代の録音なの?」と疑うくらい音質が良い。磁気テープ特有のヒスノイズさえ全くない。これ以上の音質は、正直言って、私は「要らない」。充分だ。そして演奏の方も「…アブラヴァネルって、すげぇ人だったんだな…」という、大変マッシヴで上手い演奏。オケの没入度も物凄く、頭の血管がプッツン(死語)しそうな大迫力をキープしている。…ユタ響も「…こんなに上手かったん?」と思うくらい完璧。サイレンはやや控え目で、脇役なのだが、オケの方が物凄い迫力なので、「…ま、いいか。」と思ってしまう。まさに「音の洪水」「正気の沙汰ではない」迫力であり、この曲の「在るべき姿」を100%表現できている。…ブーレーズの3種の録音を聴くくらいなら、是非こっちを聴いて欲しい。これは確実に満点以上である。
(★★★★★★)
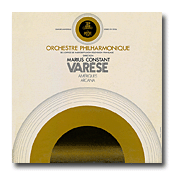
マリウス・コンスタン指揮/フランス放送フィル (before 1974)
Marius Constant
Orchestre Philharmonique De L'Office De Radiodiffusion Française
Marius Constant
Orchestre Philharmonique De L'Office De Radiodiffusion Française
Erato / STU 70726 (LP)
どうやらCD化されていないようだ。コンスタンはルーマニア出身、フランスで活躍した指揮者・作曲家。discogsで中古LPを購入した。
早速聴いていく。改訂版。まず、録音は大変良い。(勿論50年近く前のレコードなのでノイズはある。)演奏は大変丁寧なもので、オケの技術力も極上。音響を丁寧かつ大胆に、空間と時間に「慌てず急いで」配置していくタイプ。即ち、適当に流したり、のっぺりした、ヤマもオチもイミもない演奏…といったものとは全く方向性を異にする。サイレンの音も「この曲における『サイレン』の何たるか」が完全に理解できている。(…それさえ出来ていない、「冷めたピザ」のように不味い演奏も巷に多いのは全く嘆かわしい。)オケはデュナーミクの幅が広く、テンポのシフトチェンジも明快で、的確かつ面白く、そして「解り易い」。…本曲の「解り易い」演奏をバカにしてはいけない。大変貴重である。…何故か、それが出来ている人は余り多いとは言えないので。(お上品に演らないと「カッコワルイ」とでも思っているのだろうか。)…こんなにカラフルな曲を「解り易くできない」のは、指揮者としての才能が欠如していると思う。…本演奏は、一方で「鮮やかな色彩が爆発」し、また一方で「夜の静寂の芳香が仄かに漂う」…という「オイシイところ」がすべて漏れなく詰まっている。静かなところはそう演り、けたたましいところはそう演る、音楽として当たり前の「描き分け」がきちんと出来ている。(…誰でもできそうなものだが、意外とそういうことが出来ない、出来の悪い指揮者が数多存在するのだから、嘆息の一つもつかずにはいられないというものだ。)パーカッションやストリングスの熱演も手に汗握る熱中と推進力を伴い、各パートの歯切れも良く、味付けが濃い。…ちゃんと指揮者が考えて振れば、こうやって「面白くて仕方のない」演奏になる、「極上の素材」のはずなのだ、本曲は。本曲がつまらなく響くとき、それはオーケストラのシェフがヘタなだけである。…なお、サウンド・プレゼンスは「如何にもアナログ時代の、左右をド派手に分離させたステレオ!」というものではなく、かなり自然な音場空間である。かと言って直接音が弱い印象もなく、非常に上手な録音だと思う。…トロンボーンの戯けた声、そしてハープの音色が美しく空間を染め上げる。…打楽器もメリハリのある大熱演であり、奏者は皆「頭の血管浮き出まくり!」といった異常なテンションがある。金管のファンファーレも、キッチリ揃え過ぎず、少しだけバラけていることが却って「音響の束、塊」としてのインパクトを感じさせ、「複数の楽器が演奏しているのだ」という、当たり前だが、それに気付けて面白いと感じられる特色になっている。フルートがフレーズを繰り返しながらどんどん盛り上がっていくところなどは筆舌に尽くし難い熱狂があり、オケの咆哮の合間に響くサイレンの囁きや阿鼻叫喚も「これ以上はない!」とさえ言える出来。…サイレンは単にフォルテで回せばいいというものではない。サイレンの∞のダイナミックレンジが、時には呟き、時には語り、時には嘆き、時には叫ぶ!…本楽曲における「サイレンの重要性」を十全に理解できている演奏であり、単なる「無気力」や「力技」、「どっちつかず」といった曖昧模糊としたものとは無縁の、痒いところに手が届く、大変優れた演奏であることに異論を挟む余地はない。
…圧巻である。…何故、これをCD化しない?…何故、これをハイレゾで世に問わない?…Mottainai。本演奏は、21世紀の現代においても、「Amériques」の演奏という試験における答案用紙の最上位に置くべき、大変優れたものである。
(★★★★★★★☆)
カップリングは「アルカナ」。こちらも物凄い。…明らかにストラヴィンスキー「火の鳥」から持ってきたと思われるフレーズも登場する曲なのだが、この演奏も、私が今まで聴いた「アルカナ」の中で一番素晴らしい可能性がある。…コンスタン、恐るべし。
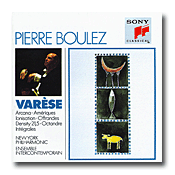
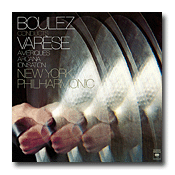

ピエール・ブーレーズ指揮/ニューヨークフィル (1977)
Pierre Boulez / New York Philharmonic
Pierre Boulez / New York Philharmonic
Sony Classical / SMK 45 844
フィジカルメディア所有。Spotifyはこちらとこちらとこちら。私が最初に入手したヴァレーズの音源(ジャケットは左上)である。勿論目当ては「イオニザシオン」の方であり、イオニザシオンにも充分魅了されたが、私がより感動したのは「アメリカ」の方である。私が所有しているCDには、「CD MADE IN AUSTRIA PACKAGED IN THE NETHERLANDS」と書かれたシールが貼られている。オーストリアでプレスされ、オランダでパッケージングされたのか…。
閑話休題。クロウ・コールは使用されておらず、改訂版での演奏である。…やはりサイレンの使い方がかなり控え目な部類に含まれる。…ブーレーズは余り「サイレン」という「楽器(?)」にはそれほど関心を寄せていなかったようだ。オケの音の方がメインで、サイレンはあくまで「脇役」に徹している。…私個人の興味としては、逆、もしくは同等の扱いの方が好きだが…。ただ、オケの充実度は完全に及第点で、クライマックスの畳み掛けるような怒濤の「音響の洪水」は充分な「混沌」「狂乱」に至っている。…この演奏辺りが「模範解答」「スタンダード」といった辺りだろう。…但し、これは録音の音量・音場・解像度等にも影響するが、もっと圧倒的な迫力が欲しい気も、やはりする。録音当時のアナログ録音技術水準も加味し、まずはこれは「満点」としたい。
(★★★★★)

ミヒャエル・ギーレン指揮/ウィーン放送響 (1990)
Michael Gielen / Radio-Symphonieorchester Wien
Michael Gielen / Radio-Symphonieorchester Wien
ORF classic / CD 3157
1990年4月5日、ウィーン・コンツェルトハウスでのライヴ録音。オーストリア放送協会(ORF)が出している2枚組、もしくは24枚組CDボックス「My RSO」に含まれる演奏。…「My RSO II」はSpotifyにある(第1部・第2部)のに、コレはないという…。何でやねん!😅…仕方ないので150ユーロ払って24枚組を買いましたさぁ!
閑話休題。早速聴いていく。ギーレンは周知の如く現代音楽のスペシャリストだし、表現主義的なところがあるので割と期待できる。クロウ・コールが出てこないのですぐに改訂稿だと分かる。…録音がメチャクチャいいな…。打楽器が近い…。凄く繊細なパーカッションの響きを拾ってくれてる…。(タンブリンのシャラシャラ…、スレイベルのリンリンリン…。凄くいい音だ…。)…凄く丁寧な音楽進行…!最高!…やっぱギーレンは裏切らなかった!最初の4分でもう「…あ、こりゃ間違いなく名演。」とすぐに分かる。サイレンの唸り声も凄いぞ!全ての楽器がきちんと「喋っている」!「叫んでいる」!…素晴らしい…。素晴らし過ぎる…!(…恍惚感…。)やっぱギーレン、解っていらっしゃるではないか…。(脳内麻薬出過ぎである。)…ぞっとする…。余りに素晴らしい…。…そうかぁ…。やっぱこういう曲はギーレンみたいな「現代音楽大好きオジサン」に振らせないとダメだな…。そして録音方式がいい。マイクの立て方。オケの目の前3メートルで聴いているかのような超オンマイクであり、全ての楽器が同じ距離に置かれている感じ。遠近感はバーターになるが、私はこうした「超オンマイク録音」の方が個人的に好きなので全く問題なし。強弱法、ゲネラルパウゼの使い方(コレ、特に超大事!パウゼも「音楽」の一部です!)、フレージング、終盤に向かっての盛り上げ方、…全く貶す箇所なしっ!完璧!文句なし!最高です!これ以上はあり得ない!
…最高です。最高です。最高です。サ、イ、コ、ウ、です!!!!!!!!…ハイ、マイ・ベストに決定。これがヴァレーズ「アメリカ」の最高の演奏です。…買ってよかった…。やっぱギーレンは信用に値する人だねぇ…。
(★★★★★★★★)

ミヒャエル・ギーレン指揮/バーデン=バーデン南西ドイツ放送響 (1991)
Michael Gielen / SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden
Michael Gielen / SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden
Warner Classics / 0724354405853
(Intercord Tonträger GmbH / INT 860.918)
(Intercord Tonträger GmbH / INT 860.918)
フィジカルメディア未所有。Spotifyになし、NMLにあり。こちら。⇒2024年12月22日、リンクが死んでいることを確認…。NMLからこの音盤は削除されてしまったようだ…。残念…。Spotifyには一応あるが、どうやら日本では聴けないようだ。(海外なら聴けるのか…?こういうことがあると、VPNサービスに手を出したくなるな…。)NMLにもdiscogsにも録音年月日データは載っていなかった。(⇒2024年12月16日に、本CDを所有している方からライナーノーツの写真を頂いた。「1991年6月録音」とハッキリ書かれている。ありがとうございました!)NMLには1929年改訂版とある。20世紀現代音楽に明るいギーレンなので、まずは一安心。…サイレンの使い方が上手いぞ!「語って」いる。「歌って」いる。…流石はギーレン、と言いたい。…但しライオンズ・ロアの音量が今ひとつだが…。オケの上手さは全く不安要素なし。パーカッションの迫力も大変良い。…超マルチ&オンマイクの、「全部の楽器の音をくまなく拾う!」という主義のもとに録音されているため、聴き応えもバッチリである。どの楽器も全て「存在感」があり、「音色のデパート」「音の洪水」状態である。…こうした録音の方が、本曲に「向いている」と思う。アンビエンス(サラウンド感、音場感)は二の次でいい。個々の楽器の「喧しいまでの自己主張」こそ、本曲には必要である。…レスピーギ「ローマの祭り」(1928)の最終楽章のような「乱痴気騒ぎ」が必須なのだ。「暴れてナンボ」である。本ページの冒頭に書いた通り、「爆演以外は笑止」な曲なのである。そこをギーレンは十全に理解できている。理想的な名演と断言できる。
(★★★★★★)

ケント・ナガノ指揮/フランス国立管 (1992)
Kent Nagano / Orchestre National De France
Kent Nagano / Orchestre National De France
Warner Classics (Apex) / 2564 62087-2
フィジカルメディア未所有。Spotifyはこちら。NMLにはなし。かつてはEratoのMusiFranceシリーズとして出ていた音源。(…ヴァレーズが「フランス音楽」かどうかは議論の余地ありだが、ドビュッシーやストラヴィンスキーの影響が顕著なので、そう言うこともできよう。…まあフランス人だしね、ヴァレーズは。)録音年は、discogsのライナーノーツの全ページの写真の末尾に辛うじて「November 1992」と書かれているので、それを採用した。
…非常に静謐な、「詩情溢れる」ヴァレーズである。…おお…。こういう、単なる「パワーの押し売り」でない、心静かに、盤上に一つ一つ駒を並べてゆくかのような演奏も、それはそれで面白さがある…。フランスオケに演らせると、ヴァレーズもこうなるのか…。(…より「ドビュッシー感」が顕著になる…。)…勿論「迫力不足」ということもなく、打楽器がドンガラガッシャンと演るところはきちんと「バカ騒ぎ」になっている。「静」と「動」の対比が美しく、的を射ているのだ。これは「大爆演ではない、フランス音楽的な残り香も漂う『アメリカ』」と言えるだろう。
(★★★★★)
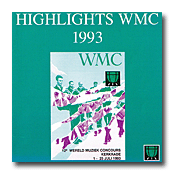
ハインツ・フリーセン指揮/トルン・聖ミカエル・ハーモニー管 (1993)
Heinz Friesen / Harmonie-Orkest St. Michaël Thorn
Heinz Friesen / Harmonie-Orkest St. Michaël Thorn
Mirasound / 399154
フィジカルメディア未所有。Spotifyにあり。こちら。トルン・聖ミカエル・ハーモニー管はオランダのオケだが、これは吹奏楽団であり、通常オケにある弦楽器セクションはいない。1863年にオランダのトルンで創立された、非常に長い歴史を持つ楽団である。(途中で2つの団体に分裂したようだが…。)フリーセン(1934-2019)もオランダ人であり、吹奏楽の世界では第一人者だったとのこと。本演奏の編曲者については情報がない。「WMC」とは、オランダ語で「Wereld Muziek Concours」、英語だと「World Music Competition」、「世界音楽コンクール」となり、1951年から4年ごとにオランダ・ケルクラーデ(Kerkrade)で開催されているアマチュアバンドのためのコンクールである。ジャンルはブラスバンド部門(狭義の、金管楽器のみの英国式ブラスバンドではなく、日本で言う「吹奏楽」の方。日本で言う吹奏楽は、オランダ語では「Blaasorkest」であり、「Brass」(真鍮)ではなく単なる「ウィンド・オーケストラ」という意味である。ドイツ語も「Blasorchester」であり、「Brass」ではない)、マーチングバンド(ショーバンド)部門、パーカッションアンサンブル部門、指揮者部門があり、招待オケやアンサンブルによるエキシビション・コンサートも含まれるとのこと。
閑話休題。ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロはいないが(日本の吹奏楽団にはコントラバスだけはいることが多い)、元々それらの楽器は本曲では余り目立たないので😅、いなくても余り気にならない。或る意味、吹奏楽団で充分だ。「代用品」以上の価値を持っている。本演奏はライオンズ・ロアの音も大きく、サイレンも非常に存在感があり、純粋に演奏レベルが高い。金管は全くハズすこともなく、打楽器・ハープも大変雄弁だ。音質も大変良い。フリーセンの指揮もかなり「攻めて」おり、超一流の演奏である。…曲の終結部の音の引き伸ばしが物凄いことになっており、ここまで伸ばしている演奏はないかも知れない。これは充分に満点以上だろう。
(★★★★★☆)
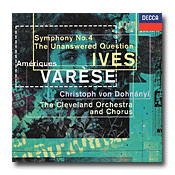
クリストフ・フォン・ドホナーニ指揮/クリーヴランド管 (1993)
Christoph von Dohnányi / The Cleveland Orchestra
Christoph von Dohnányi / The Cleveland Orchestra
Decca / 443 172-2
フィジカルメディア所有。本盤はSpotifyにもNMLにもない。(ドホナーニは選択的にしかSpotifyに音源を提供しておらず、例えばブルックナーは6番だけなかったりする。…何でやねん!)本盤は改訂版であり、クロウ・コールは登場しない。ドホナーニは祖父が著名な作曲家(エルンスト・フォン・ドホナーニ)だったことも関係するのか(但しエルンストは保守的な作風だったという)、新ウィーン楽派を始めとする20世紀現代音楽をかなり録音している。本盤はアイヴズの交響曲第4番のカップリング(メインでない穴埋め曲)であり、この曲以外にはヴァレーズの録音は見当たらないが、演奏は大変気合が入った優れた演奏で、サイレンの呻き声も非常に効果的に使用されている。…20世紀現代音楽の旗手である(はずの)ブーレーズのシカゴ響録音などより遥かに出来が良い。音質も流石はデッカ、という出来であり、大変高音質で録音されている。前述のサイレンに加え、打楽器や管楽器の咆哮も大迫力であり、メリハリに富み、大変聴き応えのある演奏に仕上がっている。こうした演奏でなければ、本曲の面白さは十全には伝わらないと思う。「漫然と演奏」するだけでは、本曲はその魅力を花開こうとはしないのだ。下降音型と共にオケがアッチェレランドしていくところなどは全くもって「指揮者がこの音楽を解っている」のが一目(一聴)瞭然であり、後半の畳みかけるようなクライマックスは、指揮者や奏者の頭の血管がブチ切れそうな超絶スピード、狂乱的な超巨大フォルティッシモになっており、全く何の不満もない。…これぞ「ヴァレーズが表現したかった« Amériques »だ」と思う。本演奏こそ、「アメリカ」の演奏でも最右翼に置いてよいものである。
(★★★★★★)




ピエール・ブーレーズ指揮/シカゴ響 (1995)
Pierre Boulez / Chicago Symphony Orchestra
Pierre Boulez / Chicago Symphony Orchestra
Deutsche Grammophon (Japan) / UCCG-1051
Deutsche Grammophon / 00028947905110
Deutsche Grammophon / 289 486 0915
Deutsche Grammophon / 00028947905110
Deutsche Grammophon / 289 486 0915
フィジカルメディア(1番目のジャケットの国内盤と、最後のブーレーズDG全録音ボックス、88枚組)所有。Spotifyはこちらとこちらとこちら。NMLはこちら。NMLには「1922年オリジナル版」と書かれているが、私が所有している国内盤のライナーノーツには「チョウ・ウェンチョンによる改訂版」としか書かれていないし、初稿にあったヴィオラソロやクロウ・コールもないため、NMLの表記が間違っているものと思われる。(…やれやれ。NMLも表記ミスが多いのかな…?サブスクはどこもいい加減だねぇ…。)…なお、一番右のジャケットのベスト盤のようなものは、ネット上にフィジカルメディアが見つからない。サブスク/オンライン専用商品かも知れない。
ブーレーズが自ら創設したアンサンブル・アンテルコンタンポランで本曲を録音しなかったのは、シカゴ響の方が資金的にも潤沢であり、大編成オケを組織しやすかったからだろう。EICは基本的には室内オケであり、本曲を演奏するにはかなり(エキス)トラを集める必要があっただろうから。(…なお、EICが全く本曲を演奏しないということはなく、マティアス・ピンチャー指揮の録音が存在するが、パリ・コンセルヴァトワール管との合同演奏である。)
演奏だが、サイレンの使い方が全曲を通じてかなり控えめで、全く目立っておらず、むしろライオンズ・ロアの方が音量が大きいくらいで、かなり物足りない。…冒頭にも書いた通り、サイレンは本曲において非常に重要な位置を占めており、サイレンが他の楽器に埋もれてしまうようでは、本曲の演奏として「失敗」とさえ言える。シカゴ響なので各楽器セクションの上手さに全く不満はないが、本録音時、ブーレーズはすでに70歳であり、若い頃のような「滾る情熱」といったものは全体に希薄である。…もっとのけぞるような圧倒的な迫力、そして挑みかかるような「狂乱の音響」が欲しい。…かと言って、ケント・ナガノのフランスオケ相手の演奏のような「詩情」も今ひとつ不足している。…曖昧なのだ。もっとどちらか、偏った方向でいいから「究極」を構築して欲しかった。…ここには、最早「古典」と化した「アメリカ」しかいない。…もっと、「たった今、この音楽が生み出された!」という新鮮さが欲しい。…不本意ながら、この点数とする。
(★★★★)


リッカルド・シャイー指揮/ロイヤル・コンセルトヘボウ管 (1996)
Riccardo Chailly / Royal Concertgebouw Orchestra
Riccardo Chailly / Royal Concertgebouw Orchestra
Decca / 460 208-2
RCO Live / RCO13006
RCO Live / RCO13006
フィジカルメディア所有。Spotifyはこちら、NMLはこちら。最初は2枚組の、ヴァレーズの全作品を網羅したCD。コンセルトヘボウ管創立125周年記念152枚組ボックスにも含まれている。本盤は、初稿をベースにチョウ・ウェンチョンが改訂した版を使用しており、「1929年版」と銘打たれている。ブーレーズ/シカゴ響盤と同じ版かな…と思っていたが、ライナーノーツ(輸入盤なので英語)を読んでみたところ、「(ヴァレーズとの共同改訂の)24年後の1996年の夏、私(チョウ)はデッカ・レコード・カンパニー・リミテッドから、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団による演奏のために、ヴァレーズのオリジナル・バージョンのスコアを改訂するよう説得された」とあり、本演奏は、クラシック・レコード業界のトップの座にいたデッカ・レコードが、本録音のために、直弟子のチョウを説得して、新たに「初稿」をベースとした「新改訂版」を作らせたことが分かる。(…すげぇなデッカ…。)なお、同じ指揮者/オケによるDVDも出ており、恐らく同じ演奏だと思うが、こればかりはDVDを買ってチェックしないと分からない。(注文済。到着待ちである。⇒配達されたので観たが、やはり全曲ではなく抜粋だった。しかしドキュメンタリーとして価値のある映像。)
初稿がベースなので、クロウ・コールが入っている。また、聞きなれない「ホー・ホー…」という、飲み物のガラス瓶の口に唇を当ててフーっと吹いたときに鳴るような音(…ってその喩え、昭和生まれの人にしか通じんな…ガラス瓶に入った飲み物なんて今時、結婚式の披露宴とかでしか見かけないもんねぇ…。あ、瓶ビールならまだ現役かな?)が聞こえる。これが「Boat Whistle」の音だろう。ライナーノーツでは、「the steamboat whistle」(蒸気船の汽笛。「ボー…」という低い音のヤツ)と書かれている。他に「cyclone whistle」も使っている、と書かれている。この「サイクロン・ウィスル」が、体育教師(笑)や鼓笛隊(マーチングバンド)の指揮者(ドラムメジャー)が吹く、日本で言う普通の「ホイッスル」のことである。サイクロン・ウィスルを効果的に使った曲といえばやっぱり、レナード・バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」(クリックするといきなり大音響が再生されるので注意!)だねぇ…。(ジェッツとシャークスのRumbleを取り締まる、クラプキ巡査の警笛の音。)
サイレンの音は少し音が高めで甲高く、個人的な好みとしてはもっと重低音が欲しいが(のちに作曲することになるイオニザシオンでは、高低二つのサイレンを使い分けるようになる)、まあそれ程減点対象という訳ではない。また、初稿にはバンダ(トランペットE♭管2、D管2、テナートロンボーン2、バストロンボーン1)も入っており、その音が遠くで鳴っているのが確認できる。14分辺りで非常に聴きなれた音型がイングリッシュホルンとアルトフルートによって奏でられる。…なんだっけこのメロディ…。ベルリオーズ「幻想交響曲」の第3楽章「野の風景」…じゃなかった…。…あ!あれじゃん!ショスタコーヴィチの交響曲第14番「死者の歌」の第1楽章と第10楽章冒頭のメロディじゃん!…もちろん作曲はショスタコの方が後(1969年初演)なので、その更に元ネタのグレゴリオ聖歌「怒りの日」から採った主題か…。…つーか、ショスタコはこのヴァレーズからメロディを拝借したのでは…!?ショスタコは交響曲第2番「十月革命に捧ぐ」(1927年出版)でサイレンを使ってるし、ソ連は初期はアヴァンギャルド(ロシア・アヴァンギャルド)も認めていたので、絶対ヴァレーズのことは知ってたと思うんだよねぇ…。(演奏や録音ではなくスコアという形で。)…という訳で、初稿の姿を確認するには最適の録音だと思う。
(★★★★★★)

フアン・パブロ・イスキエルド指揮/カーネギーメロンフィル (1996)
Juan Pablo Izquierdo / The Carnegie Mellon Philharmonic
Juan Pablo Izquierdo / The Carnegie Mellon Philharmonic
Mode / mode 58
SpotifyにもNMLにもない。現代音楽専門レーベルであるModeのクセナキス・エディションの第3弾で、同シリーズの他のCDはパラパラとSpotifyにあったりするのだが、何故か本盤は登録されていない。なので仕方なくアメリカアマゾンで中古を購入した。2021年7月3日に注文し、同月12日に到着した。…コロナ禍の中、アメリカからの発送で9日で到着というのはかなり驚異的なスピードだ。…コロナ禍と言えば、昨日(2021年7月12日未明)のウィンブルドン・テニス男子決勝をテレビで観たが(ジョコビッチが優勝)、満員の観客席、そして観客の中でマスクをしている人は、スタッフを除けば、100人に一人くらいしかいない。…あちらではもうとっくに、コロナウィルスを制圧したのだ。(制圧したつもりだけかも知れないけど。→…と思ったら違った。日本なんかより遥かに沢山の感染者が毎日出ている…。「観客は入場にあたり、ワクチンの接種証明、迅速検査の陰性結果、過去6カ月以内の感染による抗体保有の証拠などを示す義務がある」ということだそうだ。)
閑話休題。フアン・パブロ・イスキエルドは1935年チリ生まれの指揮者。12歳の頃にはシェーンベルクを好んで聴いていたという。ドイツでシェルヘンに学び、ニューヨークフィルではバーンスタインのアシスタントを務めている。オケのカーネギーメロンフィルは、カーネギーメロン大学付属の音楽院(Music School)の学生を中心とするオケだが、こうしてクセナキスやジャチント・シェルシの録音をリリースするなど、かなり現代音楽にも力を入れている。
早速聴いていく。改訂版での演奏である。セッション録音なので、流石にオケのミスはない。そして特筆すべきは、サイレンの音が「物凄く大きい!」ということである。…これは「解っている人の演奏」だ。サイレンは音が大きいだけでなく、その「完全に継ぎ目のないグリッサンド」、そしてこれまた「大変滑らかなクレッシェンドとデクレッシェンド」を作れる…という特質を存分に活かし、物凄く「語って」いる。「歌って」いる。「叫んで」いる。「主張して」いる。…そういうことなのだ。本曲で「サイレンを脇役扱いにする」ような指揮者は、この曲を理解できているとは全く言い難い。イスキエルドは「解っている」方の指揮者だった。オケの各楽器の扱いも「流している」ようなところは皆無で、全楽器が各々存在を主張し、鬩(せめ)ぎ合うが、しかし一方で「一つの美しい調和の世界」を現出させており、この曲が決して「ただメチャクチャなだけの、雑音の集合体」などではないことを、きちんと聴き手に分かりやすい形で提示してくれている。…「分かりやすいこと」は褒められこそすれ、決して貶されるべきではない。…もの凄いことなのだ、こんな曲を「分かりやすく演奏できる」のは。…そして終結部のサイレンの咆哮とフェルマータ+Lunga!…本録音が最も迫力があり、最も長い。…フェルマータは10秒以上伸ばしている!…そら、見たことか。肩書やネームヴァリューだけで演奏を選んではいけない。…こういうところに、真の名演が眠っていたりするのである。明らかに本演奏は、マイ・ベストの最有力候補の一つである。…本演奏を聴いて、それでも「ヤンソンスの方がいい」などという人がいたら、私はその人とは水と油なので、決してお目にかかりたくないものである。
(★★★★★★★)
…なお、併録のクセナキスの3曲のうち、かなりポピュラーな「ペルセファッサ」を除く2曲、「Dämmerschein」(夕暮れ、黄昏、残光、斜陽)、「La Déesse Athéna」(女神アテナ)は世界初録音であり、かつ3曲全てクセナキス本人の監修により録音されている。…正直、「Dämmerschein」などは如何にもクセナキスらしい「凄すぎる音響」で、これを聴いて「…ワケワカラン。キライ。これは音楽じゃない。」という人がいても、私はその人を軽蔑したりはしない。「La Déesse Athéna」も、パーカッションと管楽器の伴奏の中、バリトンがファルセットによる高音と低い地声を交互に繰り出しながら7分以上歌い上げるという、大変インパクトのある曲であり、「ほえぇ…なんちゅう音楽じゃこりゃ…」とビックリしてみるのも一興である。(決してオススメはしないが。😅自己責任で聴いてください。)
念の為触れておくと、クセナキスとヴァレーズにもちゃんと接点があり、クセナキス(建築家・数学者でもあった)がル・コルビュジエの助手を務めて建築したブリュッセル万博のフィリップス館で流されたのが、クセナキスの「Concret PH」と、ヴァレーズの「ポエム・エレクトロニク」であった。

ピエール・ブーレーズ指揮/グスタフ・マーラー・ユーゲント管 (2000)
Pierre Boulez / Gustav Mahler Jugendorchester
Pierre Boulez / Gustav Mahler Jugendorchester
available on Soundcloud
SoundCloudにアップされている音源。こちら。SoundCloudは本来の著作権者以外でもアップできてしまうため、演奏データが正確かどうかは、サイトの表記を鵜呑みにせずに自分で確かめた方が安全。…本録音についても投稿者が「2000年8月1日のライヴ録音だ」と書いているのに、別のユーザが「…そのプログラムは7月27日と8月2日に演奏されたはずだ。8月1日ってのはラジオで放送された日であって、7月27日が演奏日じゃないのか?」と茶々を入れていて、投稿者が「イヤイヤ!ちゃんと8月1日のライヴ録音だって放送で言ってたんだよ!演奏日が予定通りにいかないことだってあるじゃんか!」と反論してそれっきりになっていたので、私が横槍を入れ、「…そういうときは、オケの演奏アーカイヴを検索すればすぐに分かりまっせ?…ほら、ちゃんと『2000年8月1日に演奏した』って出てきますがな。」とコメントしておいた。(…マーラー・ユーゲント管も大変しっかりした演奏アーカイヴ検索システムを提供しており、トップページの右側にある「SEARCH」とある入力フォームで全演奏記録が検索できる。…日本のオケも見習ってちょ、マジで。)
閑話休題。マーラー・ユーゲント管はアバドが創立した青年オケ。(…この「ユーゲント」ってあんまり使わない方がいいのかな…。どうしても「Hitlerjugend」を想起させちゃうよね…。英語のYouthを使った方がいいかな…。)…で、肝心の演奏の方だ。…やっぱり所詮はユースオケなんだよな…。ところどころ演奏ミスがある。ブーレーズ75歳の頃の演奏だが、これが3種目。…それなりにカドはあるけど、他の超優秀な演奏を聴いちゃうと、相対的に点数を落とさざるを得ない。…多分、これだけ聴いているぶんには全く文句は出ないと思うが。…相手がユースオケなので、そんなに振り回す訳にもいかないし、そもそもブーレーズという指揮者自体、「緻密で分析的な演奏」こそ得意だったものの、「ハデに山あり谷ありの爆演を作る指揮者」じゃないからね…。あともう一匙、Something Goodがあればなぁ…。…ただ、「これで充分!充分過ぎる!」という人がいても、反論できる客観的証拠は提出できないかも。充分及第点ではあるので。…もしかしたらブーレーズの「アメリカ」ではこれがイチバンかも知れない。…少々甘めの満点を献上。
(★★★★★)
本録音は、いつもお世話になっているD様に教えていただいた。ありがとうございました!…本曲は弱小オケは演奏できない規模のものなので油断していて、bandcampみたいなところにはきっとないだろう…とは思ってましたが、SoundCloudという選択肢もありましたね…。ここはネットラジオ等で放送された音源もバンバンアップできちゃうので、一流オケの放送録音とかも多く…。抜かりました…。今後はSoundCloudもよく探すようにしますね!
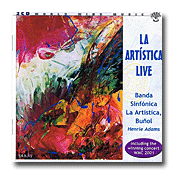
ヘンリー・アダムス指揮/ラ・アルティスティカ・ブニョール・シンフォニック・バンド (2001)
Henrie Adams / Banda Sínfonica La Artística, Buñol
Henrie Adams / Banda Sínfonica La Artística, Buñol
World Wind Music / WWM 500.075
フィジカルメディア未所有。吹奏楽版。SpotifyにもNMLにもなく、amazon music(アマプラに含まれる)にあったので聴けた。こちら。指揮者のアダムスはオランダ・トルン出身の指揮者だが、スペインを拠点に活動しているので、個人サイトもスペイン語がメイン言語である。オケはスペイン・バレンシア地方のブニョールにある吹奏楽団である。フリーセン盤のところにも書いたが、吹奏楽版でも全く「楽器の不足感」を感じない。(…聴くと、やはりコントラバスだけは参加しているようだ。弦楽器の音が聴こえる。)…この演奏も終結部の引き伸ばしが凄い。フリーセン盤と同じである。オリジナルのスコアがそうなっているのだ。フェルマータ+Lungaの指定がある。「可能な限り伸ばせ!」という指示なのだ。…この演奏もオケが全くのプロレベルであり、音をハズしているような箇所は皆無だ。これも満点超えで良い。
(★★★★★☆)

ゾルターン・コチシュ指揮/ハンガリー国立フィル (2002)
Kocsis Zoltán / Nemzeti Filharmonikus Zenekar
(Hungarian National Philharmonic Orchestra)
Kocsis Zoltán / Nemzeti Filharmonikus Zenekar
(Hungarian National Philharmonic Orchestra)
Budapest Music Center Records / BMC CD 102
フィジカルメディア未所有。Spotifyはこちら。ピアニストとして名を成し、指揮者に転向したコチシュの演奏。2002年当時、コチシュは本オケの音楽監督の地位にいた。…まずジャケ写が攻めていて中々良い。演奏も充分に気合の入ったものであり、音質も抜群に良い。…ハンガリーはコダーイやバルトーク、リゲティやエトヴェシュ、クルターグを輩出するなど、20世紀現代音楽の舞台としては充分に先進的だった。(…様々な事情で、ハンガリー国内で活躍できた人は少ないが…。)本演奏は、オケの実力も充分に高く、サイレンの咆哮、金管の絶叫、パーカッションの阿鼻地獄、いずれも全く不満なし。コチシュの指揮も、常に前のめりの推進力を失わず、大変聴き応えがある。ムチ(ウィップ)の音も大きく目立ち、バチン!バチン!と小気味良い。後半のクライマックスの「…いつまで経っても終わらないかのような、しつこいまでの反復」には、手に汗握る気魄が存分に籠められている。これぞ「爆演」であり、この、途方も無いエネルギーの塊をぶん投げられたような衝撃は、是非ナマで聴いてみたいな…と思わせる。これも全く欠点のない演奏と言って良いだろう。
(★★★★★★)
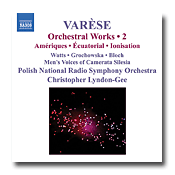
クリストファー・リンドン=ジー指揮/ポーランド国立放送響
(2005)
Christopher Lyndon-Gee / Polish National Radio Symphony Orchestra
Christopher Lyndon-Gee / Polish National Radio Symphony Orchestra
Naxos / 8.557882
フィジカルメディア未所有。Spotifyはこちら、NMLはこちら。ナクソスから出ているヴァレーズ管弦楽作品集。流石にナクソスは何でも揃っている。リンドン=ジーはイギリス出身の指揮者。ブーレーズを研究し、ミラノでマデルナの助手を務め、オルガニスト、ピアニストとしても活躍しながら、トリノで現代音楽アンサンブルを設立したり、ブーレーズ、リゲティ、ダッラピッコラらの楽曲のイギリス初演も多く振っている、現代音楽に大変明るい人である。NMLによれば、1929年版(チョウ・ウェンチョン改訂版)である。1929年版は初稿がベースのため、クロウ・コールやボート・ウィスルが入っている。サイレンの音が大変大きく、ストラヴィンスキーを思わせる、叩きつけるような音響は実に力強い。…ナクソスの録音は初期こそ貧弱だったが、21世紀以降はもう完全にメジャーレーベルと遜色ない音質になっており、本録音も全く録音が悪いという印象はない。ポーランド国立放送響は20世紀現代音楽はお手の物のオケであり(ポーランドもハンガリーに負けず劣らず、多くの現代音楽作曲家を輩出している)、聴いていて全く物足りなさはない。クロウ・コールのけたたましい響きも強烈で、こうした演奏なら「…クロウ・コール、アリじゃね?」という気を起こさせる。(…感化されやすい私…😅)遠くから聴こえるバンダの音も確認。これは確かに初稿ベースだ。シャイー盤で気付いたショスタコーヴィチ「死者の歌」の旋律も確認。ヴィオラのソロ、「ズン、チャ、チャンチャンチャン」という「急に入ってくる通俗音楽」、フルートの旋律に聴かれる無調っぽい響きなど、改訂稿にない「無国籍な響き」が次々と現れては消える。…これはやっぱり初稿ベースの方がちょっと面白いかも知れない。リンドン=ジーの指揮も冴えており、バラエティに富む造形、2秒以上のゲネラルパウゼの挿入など、メリハリが効いていて大変良い。(…唯一、ライオンズ・ロアが余り良く聴こえない気はする。…オカシイな…と思って、聴き終わった後にもう一度聴き直して見たが、やはりライオンズ・ロアは登場はするものの「余り活躍していなかった」。)…しかし、これももう、貶す余地がない名演の一つだろう。(…こういうのを聴いてしまうと、なぜブーレーズがあの程度の録音しか残せなかったのかが疑問だ…。)
(★★★★★★)
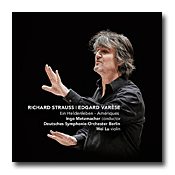
インゴ・メッツマッハー指揮/ベルリンドイツ響 (2007)
Ingo Metzmacher / Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Ingo Metzmacher / Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Challenge Classics / CC72644
フィジカルメディア未所有。Spotifyはこちら、NMLはこちら。メッツマッハーは2007年から2010年までベルリンドイツ響の首席指揮者に就任していたが、2012年から2016年にはトゥガン・ソヒエフが受け持ち、2017年からはロビン・ティチアーティがその職に就いた。メッツマッハーは2010年に、オケの予算が潤沢でないことを理由に、2012年までの契約を途中で破棄し、首席指揮者を自ら降りている。(…何が不満だったのだろうか。…要は「報酬が安い」と思ったのか。)その後2年間は首席指揮者を置かなかったのだが、日本語版ウィキペディアでは2012年までメッツマッハーが務めたことになっている。(…日本語版ウィキペディアは詰めが甘いなぁ、相変わらず…。)
閑話休題。NMLには1922年オリジナル版の表記あり。確かにクロウ・コールが聴こえる。(…但し、猛烈に小さい音。)ボート・ウィスルも聴こえ、サイレンはかなり大きな音で収録されている。他にも、初稿ベースの版で聴こえる特徴が一通り揃っている。…しかし、正直「覇気の感じられない、流した演奏」に聴こえる…。特に前半。もっと血管がキレそうな演奏でないと…。かなり大人しい、カジュアルな演奏だ。こういうのは余り高く評価する気になれない。後半の疾風怒濤の箇所は流石に良い出来だが、そこまでの経過が余り良くない。…このくらいが「平均点」なのかも知れない。
(★★★★)

ブガッリョ=ウィリアムズ・ピアノ・デュオ・アンド・フレンズ (2008)
Bugallo-Williams Piano Duo & Friends
Bugallo-Williams Piano Duo & Friends
wergo / WER 6708-2
フィジカルメディア未所有。NMLはこちら。作曲者自身の編曲ではなく、奏者の一人、エレナ・ブガッリョ(1971年生まれ、アルゼンチン出身、スイス在住)編曲による2台ピアノ8手(連弾2台=奏者4人)版。本ページ冒頭で紹介した沼野雄司の著作には「ヴァレーズ本人の編曲による2台ピアノ8手版があり、その楽譜は21世紀になって初めて発見された」と書かれているのだが、こちらで売っている楽譜が「作曲者自身の編曲、ブガッリョ校訂」とあるので、まさしくこれだろう。(…但しリコルディから出ている楽譜は2011年出版だが、本演奏は2008年である。)エレナ・ブガッリョ(これはアルゼンチンの標準語であるスペイン語読み。彼女はアルゼンチンを出てアメリカの大学で学び、博士号はコンロン・ナンカロウの研究で取得、現在はスイスのバーゼル大学に在籍しているそうなので、「ヘレナ・ブガッロ」と表記すべきかも知れない)は20世紀現代音楽を主に扱うピアニストであり、本盤のカップリングはモートン・フェルドマンの作品である。…フェルドマンの晩年の作風とヴァレーズの作風は「殆ど正反対」にも思えるが、HMVの記事によればフェルドマンはヴァレーズに大変傾倒していたそうで、この二人の作曲家を並べたのは偶然ではないとのこと。…フェルドマンがヴァレーズに傾倒していたなんて話、初めて知った…。…でも英語版ウィキペディアを読むと、フェルドマンは1973年に「エドガー・ヴァレーズ教授」と自称するようになった…とあり、強ち間違いという訳でもなさそうだ。フェルドマンも生涯を通じてかなり作風が変化しており、大規模なオケや大きな音を使った曲もあった。
閑話休題。初稿版をベースにしていることが分かる。…しかし、やっぱり「サイレン」とかの要素はピアノでは全く表現しようがないので、かなり物足りなさは残る。…そもそもこんな「ピアノなどではとても表現し切れないような気宇壮大な曲」を、何故ヴァレーズ自身がピアノ・リダクションなどにしようと思ったのか…。(…まあ、少人数でも演奏できるようにして、楽譜を売って生活の足しにしようと思ったのだろうな…。多くの作曲家は、そうしたピアノ・リダクションを作って、少しでも苦しい生活を楽にしようとしてきた歴史がある。…沼野雄司の著作でも、私と全く同じ理由から「謎だ」と書かれている。沼野雄司は、ジョージ・アンタイルの「バレエ・メカニック」に触発されて書いてはみたが、結局お蔵入りにしたのでは、と予想している。)…それなりに面白いことは面白いが、オケ版に比べたらその魅力は「半分以下」といったところだろう。
(★★★★)
ピアノの奏者は以下の通り。
エレナ・ブガッリョ - Helena Bugallo
エイミー・ウィリアムズ - Amy Williams
エイミー・ブリッグス - Amy Briggs
ベンヤミン・エンゲーリ - Benjamin Engeli

ベルトラン・ド・ビリー指揮/ウィーン放送響 (2009)
Bertrand de Billy / Vienna Radio Symphony Orchestra
Bertrand de Billy / Vienna Radio Symphony Orchestra
col legno / WWE1CD20295
フィジカルメディア未所有。NMLにあり。こちら。改訂版を使っている。…静謐も重んじた、「非爆演タイプ」の演奏である。…ブーレーズやナガノと同じ路線。演奏の質は決して悪くないのだが、…やっぱりフランス系は、こういう路線を選ぶのかなぁ…。(ド・ビリーはフランス人。ナガノはアメリカ人だが、オケはフランス。)ブーレーズやナガノと同様、サイレンが目立たない。あくまで「味付け」程度にしか使われていない。「押しが弱い」感じは、どうしても否めない…。もっと「暴力的」でないと、曲が活きないような気がするのだが…。「コレジャナイ」感が…。ムチ(ウィップ)の音も何だか頼りない。終結部付近のクライマックス部分も「消化不良」を起こしている感がある。…どこかまだ「遠慮がある」のだ。「目一杯」、「出力120%」になっていない。…それじゃダメなんじゃ…。個人的には余りオススメできない。
(★★★★)
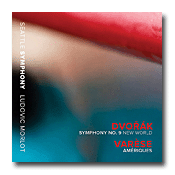
ルドヴィク・モルロー指揮/シアトル響 (2011)
Ludovic Morlot / Seattle Symphony Orchestra
Ludovic Morlot / Seattle Symphony Orchestra
Seattle Symphony Media / SSM1006
ライヴ録音。フィジカルメディア未所有。Spotifyはこちら、NMLはこちら。改訂版を使用。シアトル響で次々と「20世紀現代音楽の定番」を録音した、個人的にお気に入りのモルローによる演奏。カップリングはドヴォルザーク「新世界」であり、「アメリカ」をコンセプトとしたアルバム構成になっている。…録音の良さも関係すると思うが、冒頭から各楽器の分離が良く、音響が立体的で、どの楽器もマスに埋もれておらず、「この曲はこんなに多くの楽器の音で構成されているのだ」という「当然の事」が改めて浮き彫りにされ、それだけでもう演奏に引き込まれる。…サイレンの音が非常に大きく入っており、殆ど「協奏曲のソロ楽器」並の扱いになっている。(オケの最前列で鳴らしているかのようなサウンド・プレゼンス。)ライオンズ・ロアも然り。…ほうらね?😁「解ってる人」の演奏は一発で「…あ、違う。」って気付けるだけの内容がある訳ですよ。こういうことなんです。ヴァレーズにだって「ウマイ演り方」がある。漫然と、よくこの音楽の価値・意味を理解せずに振ってしまったら、こういう演奏には、まず、ならない。このページに並べただけの演奏を聴き比べても、すぐに「優位性」に気付けるくらいの演奏になっている。…私がモルローを個人的に推しているのはこういうことです。この人は数少ない「解ってる指揮者」です。この人は信用していい。裏切らない。…サイレンは本当にステレオの中央に定位しており、どの楽器よりも音量が大きい。…私が誰からも情報・示唆を得ずに、以前から思っていたのは、本曲は「サイレン協奏曲」という側面が確実にある、ということ。…オマケじゃないんですよ。サイレンは「主役」です。…じゃなきゃワザワザ「サイレン」なんてモノを使わないでしょ?…そうした以前からの私の考えを、殆ど初めて実践してくれたのが本演奏。(…なので、「サイレンの音が他の楽音に埋もれていて良く聴こえない」なんてのは、ハッキリ言って「論外」です。解ってないです、そういうヤツぁ。)…終結部の音のフェルマータも、メチャクチャに長い。…解ってるねぇ、ホントに…。…改めてスコアを読んでみると、終結部は「フェルマータ+Lunga」、つまり「可能な限り音を伸ばせ!」であり、強度記号は「sffff」(スフォルツァンドにfを3つ追加!)になっている。終演後は拍手喝采、観客も大興奮!…そりゃあそうだ。当然の反応である。…勿論本録音は満点以上。ヴァレーズ「アメリカ」の最高の演奏の一つに数えて良いと思います。
(★★★★★★★)

マリス・ヤンソンス指揮/ロイヤルコンセルトヘボウ管 (2011)
Mariss Jansons / Royal Concertgebouw Orchestra
Mariss Jansons / Royal Concertgebouw Orchestra
RCO Live / 814337018078
ライヴ録音。フィジカルメディア未所有。Spotifyはこちら、NMLはこちら。1929年チョウ・ウェンチョン改訂版。シャイー盤と同じ版である。1929年版はコンセルトヘボウのために改訂された版なので、同じオケでヤンソンスが使うことになるのはごく自然な流れだ。…しかし、ヤンソンスという人がヴァレーズ「アメリカ」を2回も録音しているのは不思議だ。この人がこういう「前衛とも言える音楽」が好き、得意、というのは寡聞にして知らない。…正直、余り期待せずに聴き始めたが(私が極度のヤンソンス嫌いなのは、当サイトの読者であればご存知だろう)、音質も良く、演奏も中々丁寧で、良い印象だ。…オケは名門コンセルトヘボウなので全く危なげないし、ダイナミックレンジも大きく、かなり聴き応えのある演奏になっている。クロウ・コール、ボート・ウィスル、ライオンズ・ロア、サイレンは「脇役」的な扱いだが、ボート・ウィスルだけは他の録音より音量がかなり大きめで、オケの色彩は豊かである。ハープも美しく、ショスタコ14番のメロディも趣のある「思わせぶりな」吹き方。ヴィオラの微分音を含むソロ、その後に続く「ズン・チャ・チャンチャンチャン♪」も、ちゃんと埋もれないように強調して演奏させている。…惜しいのはサイレンの音の高さで、かなり甲高い音のもの(恐らく小型、もしくは電子サイレン)を使っており、もう少し重低音が出せるタイプが良かった。(ヴァレーズが初稿で指定した「ニューヨークの消防署で使っているようなサイレン」がどのような音を出すものか分からないが、私の個人的な嗜好からすれば、もっと重低音の出る「重たい感じの音色」が良い。…本ページの冒頭に書いた通り、改訂稿でのヴァレーズのサイレンに対する要求は「重厚でパワフルなもの」である。…こういうところが、「ヤンソンスは藝術家としては二流」と、私のようなド素人にツッコまれてしまう「詰めの甘さ」を露呈しているところである。…こうした細かなところでいつも「馬脚を露わす」のが、逆にヤンソンスらしい。)…終結部、全く音をフェルマータさせていない。むしろスタッカート気味に「ブチッ」と音を切ってしまっており、これはいただけない。強度も「sffff」を実現できているか?といったところ。…こういう演奏は余り推薦したくない。そこまで到達できていない。
(★★★★)
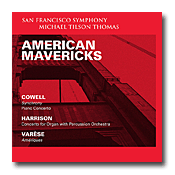
マイケル・ティルソン・トーマス指揮/サンフランシスコ響 (2012)
Michael Tilson Thomas / San Francisco Symphony Orchestra
Michael Tilson Thomas / San Francisco Symphony Orchestra
SFS Media / 821936-0056-2-0
(SACD Hybrid)
ライヴ録音。フィジカルメディア未所有。Spotifyはこちら。NMLはこちら。フィジカルメディアはSACDハイブリッド。アメリカ出身の指揮者とアメリカオケによる「アメリカ」である。改訂稿を使用。ストラヴィンスキーを思わせるバーバリックな打撃の連続の中で、野獣のように荒々しく雄叫びを上げるサイレンの存在感が素晴らしい。…前述している通り、この曲で「サイレンを協奏曲のソロ楽器並の扱いにしない」指揮者及び録音エンジニアは、音楽的センスが不足している。そういう人達には手に負えない音楽なのだ。…その点、MTTに抜かりはない。本演奏の特徴は如何にもMTTらしい、「頻繁なテンポの緩急の交代」で、曲想に合わせて細かくテンポを変え、叙情的なところでは遅めに、暴力的なところでは速めにテンポをコントロールし、巧みに変化をつけている。…私が一番嫌う「一辺倒で単純な、気の抜けた棒の振り方」をしていない。…この難曲にきちんと真正面から挑み、曲想が活きるよう、しっかり味付けをし、スパイスを効かせているのだ。こういう細かな藝當が全然出来ない人がヤンソンスで、こういうところで「藝術家としての才能の差」が簡単に露呈してしまう。…そしてやはり、本演奏の終結部の「フェルマータ+Lunga」は「メチャクチャ長く引き伸ばし」、「sffff」も実現できている。…だって、そうやれってスコアに書いてあるんですよ?遵守して当然でしょう?そういうのを無視するから、結局は中途半端な演奏になってしまうワケでしてねぇ。…本盤はちゃんと「やるべきことをやっている」。これは推薦に値します。
(★★★★★★)
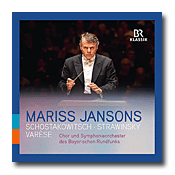
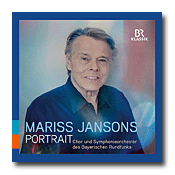
マリス・ヤンソンス指揮/バイエルン放送響 (2015)
Mariss Jansons / Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Mariss Jansons / Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
BR-Klassik / 900161
BR-Klassik / 900157
BR-Klassik / 900157
フィジカルメディア未所有。Spotifyはこちらとこちら、NMLはこちら。NMLによれば1922年の初稿を使っているとのこと。(…1929年版との違いはよく分からない。)クロウ・コールの音が凄く目立つ。ボート・ウィスルの音も聴こえる。バンダの音も聴こえる。…やはり終結部の音を全く伸ばしていないことや、ライオンズ・ロアやサイレンが前半殆ど目立たず、全体を通じてテンポの緩急に全く神経を使っていないのも気になる。「ヤンソンスならでは」の個性的な工夫が聴かれず、「…まあ、楽譜が読めて、オケを振るのが生業の人なら、このくらいは誰でもできるでしょ?」という、全く「カドのない、平坦な演奏」であり、聴くべきものは皆無と言って差し支えない。…本曲を2回も録音しているのはブーレーズとギーレン、そしてヤンソンスくらいなので、「…もしかしたら本曲に特別な思い入れでもあるのかな?」と少しだけ期待したが、恐らくこれでも「ヤンソンスの本気!」なのだろう。決して惰性や他人からの強制で本曲を振ったのではないのだろうが、やはり「Lack of talent」で「Ungifted」な人の演奏、という印象はどうしても拭えない。…終盤に入ってもオケ・指揮者が全く「熱中しておらず」、「余裕綽々」なのが伝わってきてしまい、鼻白む。「如何にもヤンソンスらしい」。
(★★★★)

マティアス・ピンチャー指揮
パリ国立高等音楽院管、アンサンブル・アンテルコンタンポラン (2015)
Matthias Pintscher
Orchestre du Concervatoire de Paris, Ensemble InterContemporain
パリ国立高等音楽院管、アンサンブル・アンテルコンタンポラン (2015)
Matthias Pintscher
Orchestre du Concervatoire de Paris, Ensemble InterContemporain
available on youtube
youtubeで発見。2015年2月3日、フィラルモニ・ド・パリ、ラ・グラン・サル・「ピエール・ブーレーズ」(2015年1月に杮落とし、2,400席。会場の中心から最も遠い座席でもたったの32メートルしか離れていないという、日本の設計事務所による建築物で、EICとパリ管の本拠地となっている)でのライヴ録画。EICの公式動画である。フルHDの画質。こちら。改訂稿(リコルディ社出版)での演奏。EICは基本的に室内オケなので、パリ・コンセルヴァトワール管との合同演奏となっている。映像付きの方が楽器構成や台数、どこでどういう楽器が鳴らしているかなどが分かって良い。…が、やはりサイレンの音が小さく、そして甲高いのが痛い。また、テンポの緩急にも余り気を使っておらず、終結部の伸ばし方も「中くらい」といった感じで、モルローとかの超名演を聴いてしまうと、やや物足りない。コンセルヴァトワール管という若手オケを使っていることも、ピンチャーが冒険できていない理由の一つかも知れない。
(★★★★)

ファビオ・ルイージ指揮/ミラノ・スカラ座フィル (2015)
Fabio Luisi / Filarmonica della Scala
Fabio Luisi / Filarmonica della Scala
available on SoundCloud
SoundCloudにアップされている音源。こちら。(ネットラジオの録音なので最初はルイージへのインタビュー、演奏は10:12から。)2015年1月12日、ミラノ・スカラ座劇場でのライヴ録音。…しかし、スカラ座フィルなんてオケでも結構頻繁にこういうヴァレーズとかの20世紀現代音楽、演奏してんだねぇ…。ビックリした。ムーティとかシャイーとかエトヴェシュとかが結構ヴァレーズ、振ってんのよ…。…まあムーティは団員の総スカンを食らって解任されちゃったけど…。スカラ座フィルは大変しっかりした演奏アーカイヴ検索システムがあり、ちゃんと演奏記録を確認できたので、間違いない。(…こういう演奏アーカイヴ検索システム、どのオケも備えて欲しいなぁ…。有名オケなのにこういうシステムがないところ、結構いっぱいあるんだよねぇ…。…特にNHK響!前はPDFで演奏記録を公開してたのに、何でページリニューアルで全部削ったんだよ!バカじゃねぇのか?…こちとら受信料はもう30年以上毎年キッチリ、今はBS料金含めて口座自動引き落としで納めてんだから、もうちっとしっかりせえや!2022年からはこのルイージを首席に迎えるんだろ?…演奏アーカイヴ検索システムくらい備えろや!…仮にも日本でイチバンを自負するオケなんだろ!?世界に対してハズカシイぞ!)
…コホン。取り乱してしまった。閑話休題。聴いていく。改訂稿での演奏。…ルイージは私が認める数少ない「お気に入りの指揮者」であり(エラそうでスミマセン)、「…何かしらやってくれてるのでは?」と期待したが、やっぱり期待通り、というか期待以上であった。フレージングが物凄く工夫されていて、ちゃんと「語っている」んですよ。きちんと「筋書き」を考えて、「…こうやると面白くなるんじゃない?」という、全体の構成を予め緻密に設計した上で振ってます、間違いなく。…こういうのさぁ、「指揮者だったらこのくらいちゃんとやってよ!」って、いっつも思うワケですよ。(…しょっちゅう引き合いに出して申し訳ありませんが)ヤンソンスとかさぁ、そういうことが「全く出来てない人」だったワケでしてねぇ。そこんところ、ルイージはちゃんとやれる人なワケですよ。…ホント、なんでヤンソンスみたいな凡人があんなに出世できたんだろ…。不思議だねぇ…。(…別のページでも書いてますが、きっと「凄くイイ人」だったんだろうなぁ…。しかし優れた藝術家って、どんな分野でもそうだけど、奇人変人、キチ○イみたいな人が多いワケですよ。…笑顔がステキな、恐らく人格者であったヤンソンスは、分かりやすくて平坦な、「聴衆や楽隊に余り負担をかけない」音楽作りが気に入られたんだろうなぁ…。ワタシは「人格なんか破綻しててもいいから、とにかく優れた藝術を生み出してくれ!」とか思っちゃうので…。まあ身近なところには人格破綻者はいて欲しくないですが。😅)…なんていうくらい、このルイージの演奏は「キチンと面白い」です。オケももう、メッチャ上手い。…やっぱイタリアオケっつったら、このラ・スカラか、ローマ・サンタチェチーリア辺りがイチバンなんでしょ?…ホント、完璧ですよ。…イタリアオケ、舐めたらアカンな…。…つか、こんなにウマイんだったら、もっと録音出しゃあいいのに、オペラ以外の…。(…まあイタリア人にそういうニーズがないんだろうな…。「オペラ以外興味ありません」みたいな。)
…ビックリした。…下手すると、これがマイ・ベストかも…っていうくらい良く出来てる…。…ルイージがN響に来んの楽しみだなー…。
(★★★★★★★)
本録音の存在は、いつもお世話になっているD様から教えていただいた。ありがとうございました!超名演でした!

クリスティアン・バルディーニ指揮/カリフォルニア大学デイヴィス校響 (2015)
Christian Baldini / UC Davis Symphony Orchestra
Christian Baldini / UC Davis Symphony Orchestra
Centaur / CRC 3879
アメリカのレーベル、Centaurから2021年に発売されたライヴ音源。発売は2021年だが、録音は2015年である。各サブスクに満遍なくあるが(私はSpotifyで聴いた)、フィジカルメディアでも売られている。収録曲と演奏者の情報が一番正確に網羅されているのはこちらのPrestoMusicのサイトだろう。…アマゾンやHMVにもあるのだが、複数の作曲家の作品を収めたオムニバスCDなので、例によって収録曲や作曲家に関する文字情報が大変乏しく、HMVはサイト内検索で「ヴァレーズ」等で検索しても全くヒットしない。…作曲家としてのヴァレーズとCDが紐付けられていないからだ。私はHMVで、作曲家ヴァレーズに関する音源が出たらメールが届くよう設定しているが、このCDは作曲家に紐付けられていないため、勿論連絡など来なかった。「…HMVさんもアマゾンさんも、CD、売る気がないんですか?」と言いたい。商売がヘタ過ぎますよ…。買う気マンマンの私のような消費者には、もっとアピールしてくれないとねぇ…。「検索しても出てこない」とか、最早論外でっせ?HMVさん。
閑話休題。改訂版を使用。オケはUC Davis(カリフォルニア大学デイヴィス校)の付属オケ、つまり学生オケである。指揮者のバルディーニはこのオケの音楽監督を務めている。学生オケのライヴ録音…というだけでもう大体予想できるが、やはりオケのミスがあり、金管が吹き損じている箇所があるし、全体的に危うい箇所が多い。…そしてもう一つ、「アメリカ」の演奏・録音として致命的な欠点が…。「サイレンがサブ楽器扱いで音量が小さい」のである。オケ全体はエスプレッシーヴォな部類に属し、例のトロンボーンが哄笑する箇所などは、ここまでトロンボーンに「大笑いさせた」演奏は皆無と言ってよい、という程に異彩を放っている。…がしかし!肝心の!肝心のサイレンの音がオケの奥に引っ込んでおり、しかも音量が他の楽器より小さい…。目立たない…。コーダの部分などは、サイレンは「全く」聴こえないのだ。…惜しい…。実に惜しい…。他の録音の箇所にも書いているが、本曲のサイレンは絶対に「本日の主役!」(笑)の扱いでなくてはならない。…曲自体を聴けば、「オケに埋もれさせてはいけない!」ということくらいは、「音楽の演奏に携わる者としてのセンス」として、自ずと気付いて欲しい。…伊達や酔狂でわざわざ「サイレン」なんて「楽器」をオケに加えますか?フツー。「隠し味程度で良い」なんて、本気で思ってる?…そういうことにまずは気付けないようでは、お里が知れるというものだ。…もしこれでサイレンの音が大音量で収録されていたら、点数に★を2つは追加していた。…そのくらい、本曲ではサイレンは重要だ。…よって、不本意ながら、この点数とする。
(★★★★)
本盤の存在は「カルミナ・ブラーナ同好の士」I様から教えて頂いた。いつもありがとうございます!

フランソワ=グザヴィエ・ロト指揮
バーデン=バーデン・フライブルク南西ドイツ放送響 (2016)
François-Xavier Roth / SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg
バーデン=バーデン・フライブルク南西ドイツ放送響 (2016)
François-Xavier Roth / SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg
available on the official site of the
Orchestra
オケの公式サイトで公開している2016年5月8日のライヴ録画。こちら。フルHDの解像度がある(通信環境に応じて5種類の画質が選択できる。自動・最高画質・高画質・中画質・低画質)。SWRはyoutubeに公式チャンネルも持っているが、そちらでは公開していない。オケの創立70周年記念演奏の一つだが、本オケはこの年、長らくドイツの現代音楽を牽引した歴史に終止符を打ち、シュトゥットガルト放送響と合併してSWR(南西ドイツ放送)響に生まれ変わることになる。(本拠地もシュトゥットガルトに移転している。)
閑話休題。改訂版を使っている。↑のピンチャー指揮の動画ではサイレンとライオンズ・ロアがほぼ全く映らないが、こちらはサイレンがバッチリ、ドアップで映っている。(…この曲の映像作品でサイレンを映さない、というのは正直、「ナイ」。…そこもピンチャーの演奏を、映像含めて褒められないところ。)…ロトの指揮姿も、ピンチャーのカジュアルな、余裕をブチかました指揮姿に比べると、とてもメリハリのある、分かりやすくて気合の入った指揮ぶりであり、こうした細かな「加点ポイント」が本映像の価値を高めている。また、その明快な指揮姿から紡ぎ出される音楽もきちんとカドがあり、しっかりと指揮者が「構成」を考えて振っているのが分かる。デュナーミクやフレージング、アーティキュレーション、テンポの緩急やパウゼの入れ方もピンチャーより遥かに細かく、ピンチャーが如何に「いきあたりばったり」で振っているか、分かってしまう。度々大写しになるサイレンも重低音の充分な、「この曲にあったサイレン」を用いており、好感が持てる。(神は細部に宿るのである。)また、映像としても藝が細かく、ちゃんとその時に特徴的なフレーズを演奏する楽器をアップにしている。トロンボーンが吹くとき、ピッコロが吹くとき、ホルンが吹くとき、サイレンが鳴るとき、ティンパニが連打するとき、ムチやカスタネットが打つとき…。流石は「放送局」の映像だ。オーケストラ映像としての基本がきちんと出来ている。(…上記のピンチャーの映像は、その辺が大変弱い。素人編集の域を出ていない。)…後半のクライマックスに向かうに連れ、カットワークも大変細かくなり、映像作品としても一級の出来になっているところが本当に素晴らしい。そして勿論、最後のフェルマータ+Lungaもメチャクチャ長く伸ばしている。…こういうことである。同じ映像作品でも、ピンチャーのは指揮も演奏も映像もシロウトの域、こちらは全て「プロの仕事」。…同じようでいて、その価値は全くレベルが違う。映像にするならこうでなくては。大満足。
(★★★★★★)
なお、「アメリカ」終演後、女性アナウンサーの解説の後、そのまま映像は、本オケのコンマスを務めるクリスティアン・オスターターク(Christian Ostertag)のヴァイオリンによるレナード・バーンスタイン「セレナード」、そしてベートーヴェン交響曲第5番と続く。「運命」は会場の拍手が全く鳴り止まないうちに、ロトが指揮台に飛び乗った瞬間に「ドカン!」と演奏が始まる…という「演出」がなされている。…人口に膾炙した「運命」である。こういう「サプライズ」でいいのだ。…しかも近年流行りの、「バカみたいな提示部の繰り返し」を省略した、20世紀中盤には標準的だった演奏スタイル。(…まあ、オケの音には少し、ピリオドスタイルの香りがするが…。)…私は、ベト5という「世界一メジャーなクラシック曲」まで提示部の繰り返しをするのは、完全に時代の遡行であり、なんかアホみたいで好きになれない。音楽の流れ、ノリを堰き止めてしまっており、もったいない。レコードがなかった19世紀以前じゃないんだから、幾らなんでも「運命」で提示部を繰り返すのは「衒学的に過ぎる」…と思う。(…まあ、本演奏でも最終楽章は繰り返しをやっているが…。…やらなきゃいいのに…。)
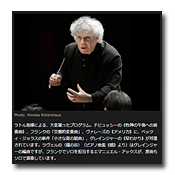
サイモン・ラトル指揮/ベルリンフィル (2016)
Simon Rattle / Berliner Philharmoniker
Simon Rattle / Berliner Philharmoniker
available on Digital Concert Hall
ベルリンフィルの会員制サイト、ディジタル・コンサートホールにある映像。こちら。2016年6月18日のライヴ。クロウ・コールやボート・ウィスルが聴こえるので初稿版ベースであることが分かる。
…悪くはないんだけど、あんまり「面白い」とは言えないかな…。聴いていて全くトキめかない。アツくならない。「演出」が弱い。ただ楽譜を見ながら、それっぽく音を繋げただけ、それ以上の創意工夫がない。この曲の特別な魅力を、ラトルがちゃんと理解できているとは、全く思えないです。「これで充分だろ」と思ってる。…コレなんですよねぇ…。ラトルの振ったベルリンフィルやロンドン響など、みんなそんな感じ。ホントですよ?私がベルリンフィルやロンドン響という「楽壇の巨人」に「やっかみ」やら「嫉妬心」やら「斜に構えた見方」等の、何らかの偏向的バイアスをもって見ているワケではないんです、恐らく。ちゃんと虚心坦懐に聴いてますって。…しかし、どうしたって、これは「フツー」過ぎます。これがヴァレーズ「アメリカ」の「感動的な演奏」とは、どうしても、思えない。…もしかしたら、録音のせいかも知れません。ダイナミックレンジがめっちゃ狭い。ずっと同じ音量で演ってるように聴こえるのは、もしかしたら録音技師が「音量の均一化」(ノーマライズ)をしちゃってるのかも知れない。…そんなことしたら、どんな音楽より幅広いダイナミックレンジが必要なオーケストラ曲には致命的だ。演奏者の演出を完全にスポイルすることになってしまう。…まあでも、テンポの緩急やパウゼの方もほぼ工夫されておらず、次から次へとフレーズを、何の意味も考えず羅列してるだけ。…こいつぁ、アクセントとかフレージングとか、そういう技術を知らんのか?…とか思っちゃうワケですよ。…なので、デュナーミクの方も恐らくラトルは何も指示できていないでしょうね…。「ヤル気がねぇのかコイツは?」…とか思っちゃうんですよ。…全然推薦できない演奏です…。
(★★★★)
…すっかりディジタル・コンサートホールのことを忘れていた。…ヴァレーズは20世紀現代音楽の古典だから、きっと沢山あるだろうな…と思って検索したら、3つも見つかった。😅

フランツ・ウェルザー=メスト指揮/クリーヴランド管 (2017)
Franz Welser-Möst / The Cleveland Orchestra
Franz Welser-Möst / The Cleveland Orchestra
Cleveland Orchestra / TCO0001D
フィジカルメディア未所有。Spotifyはこちら、NMLはこちら。NMLによれば、1929年チョウ・ウェンチョン改訂版。(…ではない。後述。)…ウェルザー=メストは正直あんまりいい印象を持っていない…。あんまり期待せずに聴く。…お!?…凄くフレーズのメリハリがあっていい感じ…!録音もいいし…。そうか、ウェルザー=メストは2002年から2021年の現在まで、何と20年近く音楽監督を…。そんだけ長くやれてるってことは、アメリカの聴衆に受け入れられてるってことだな…。…思ったよりはいい。…なお、1929年版ってのはウソだな。…だってクロウ・コールもボート・ウィスルも登場しないもん。初稿版特有のフレーズもなし。これは1927年改訂版の方です。(1929年チョウ・ウェンチョン改訂版とは、「初稿」をベースに改訂した版を指します。)…NML…。ヴァレーズ「アメリカ」だけでもう、かなーり版表記がいい加減であることがバレちゃいましたねぇ…。NMLはSpotifyとかと違って、そういうところはしっかりしてるもんだとばかり思ってたんですが、「Et tu Brute?」…。まあいいや。
…これは「前のめりの『ノリと勢い』で押し切った超ヤケクソ演奏」です。(…分かりにくいですが、最大限に褒めてマス。)「爆演」です。クリーヴランド管なのでオケはメッチャ上手いし、サイレンは少し音量が不足気味ですが、重厚さ(音の低さ)は問題なし。「冷静と情熱(のあいだ)」の描き分けもソコソコ上手いです。ドビュッシー感とストラヴィンスキー感とシェーンベルク感、そしてそれらをミキサーにかけて文字通り"Chaos"にした「ヴァレーズ感」がよく出てます。大名演ではないですが、及第点です。
(★★★★★)

アレン・ティンカム指揮/シカゴ・ユース響 (2018)
Allen Tinkham / CYSO's Symphony Orchestra
Allen Tinkham / CYSO's Symphony Orchestra
available on youtube
2018年5月20日、シカゴ・シンフォニー・センター、オーケストラ・ホールでのライヴ録画。オケの公式動画。こちら。フルHD画質。指揮者のアレン・ティンカムはアメリカ・ロードアイランド州(アメリカ独立13州の一つだが全米50州で最小の面積、滋賀県と同じくらい)生まれ、イギリス系とレバノン系の両親を持つ指揮者。2001年からこのオケの音楽監督を務めている。オケはその名の通り青年オケで、18歳までの未成年だけで構成されているとのこと。出身者が世界中のオケで活躍している、養成機関でもある。
閑話休題。…ユースオケ、しかも18歳以下とのことなので、余り期待せずに聴いていく。…ああ…。やっぱり冒頭のアルトフルートの音がもう…。(…楽器が良くないのかな…?音がかすれている。)金管も始まって1分でもう不安感が…。…ハープが3台いる。フルート属は5人。ティンパニを除く打楽器が9名なので1927年版。音質が良く、打楽器の迫力も素晴らしいし、サイレンの音も甲高くなく、音量も大きいのは好印象。人種は白人とアジア人が中心。(…黒人はファゴット奏者に一人いるだけかな…。インド系っぽい子がパーカッションに一人、東南アジア系が一人コントラバスに、中南米系が一人ホルンにいるか…。…ユースオケを見ていつも思うけど、南北アメリカ原住民系(インディアン・インディオ系)とか西アジア系は、本当に欧米のオケにいないねぇ…。)ティンカムの指揮はやはりゆっくり目かつイン・テンポの安全運転。全く冒険をしていない。…まあ仕方ないね…。
(★★★☆)
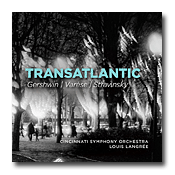
ルイ・ラングレ指揮/シンシナティ響 (2019)
Louis Langrée / Cincinnati Symphony Orchestra
Louis Langrée / Cincinnati Symphony Orchestra
Fanfare Cincinnati / FC-016
フィジカルメディア未所有。Spotifyはこちら、NMLはこちら。1922年初稿使用とある。…確かにクロウ・コールが入るね。ルイ・ラングレは1961年フランス・ミュルーズ生まれの指揮者。…しかし、…何かオケの人数、少なくないですかね…。凄く音が薄いんですが…。全パート、半分くらいの人数しかいない気が…。50人くらいで演ってる感じ。…しかしクロウ・コールのはっちゃけ方だけは全録音の中で随一で、こんなに遊んでる演奏は他にはない。…これ、マジで「室内オケ編成版」ってな感じ。絶対にこれ、楽譜通りの楽器数、揃えてないよ。…ただ、その室内楽的な音の薄さが、逆に各楽器のフレーズを明確に聞き取らせてくれる…という副次的なアドバンテージを生んでいるのは面白い。…もしかしたら、ラングレがその効果を故意に狙った可能性もゼロじゃないな…。ラングレのレパートリーを眺めると、モーツァルトが圧倒的に多く、あとはベルリオーズとかフランクとかショーソンとか、せいぜいロマン派止まりなんだよね…。アメリカオケだからガーシュウィン、ストラヴィンスキー、コープランドとかの「お国モノ」も録音があるけど、少ない。…「大艦巨砲主義的なヴァレーズの『アメリカ』を、敢えて室内楽的に演ったらどうなるか?」というサジェスチョンとして受け止めることができるなら、本盤は一聴の価値があるだろう。…面白いことをする人だねぇ…。
(★★★★☆)
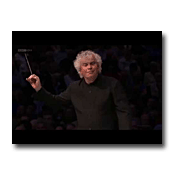
サイモン・ラトル指揮/ロンドン響 (2019)
Simon Rattle / London Symphony Orchestra
Simon Rattle / London Symphony Orchestra
available on youtube
youtubeに上がっている非公式動画。2019年8月2日、ロイヤル・アルバート・ホールでのプロムス2019のライヴ録画。非公式なので解像度はそこそこ(720i/pくらいの画質、1080i/pまでは行かない)である。こちら。1921年初稿版。…おやおや…。冒頭のアルトフルートが結構ヘタクソなんですが…。シカゴ・ユース響の奏者と天下のロンドン響奏者のレベルが同じ…?…やっぱり結構難しい楽器なのかな…。(デカくて重そうだしね…。)この動画で初めてカエルの鳴き声のような「Crow Call」の実物を確認できる。手に隠れる程小さい楽器である。(両手で一つずつ持って2本同時に吹いているシーンもある。)また、ライオンズ・ロアの「演奏シーン」もこの動画で初めて確認できる。太鼓の革の中央にあるヒモを引っ張る(というか布で擦る)ことで、あのような「ギュウウウゥゥゥゥ!」という音が出る。(…獅子の咆哮というようりは、腹が減った時に鳴るお腹の音みたいだが。)ボート・ウィスルも映る。片手で持って吹いている。(奏者が一人で複数の楽器を担当するので、忙しい。)…サイレンも映るのだが、…何と「電子式サイレン」だー!!😅…小さな四角い箱の上にスピーカがついており、奏者はボリュームのツマミを操作しているだけ、手でハンドルをグリグリと回すようなことはしていない。…もうサイレンも「電子楽器」なのね…。ちなみにやっぱり使っているサイレンは1台だけである。また、かなり甲高い音で、ヴァレーズの「deep and very powerful」という指示が守られていない気が…。そして最後のフェルマータ+Lungaも、これまた守られていない。…あそこを「狂ったように」伸ばすことのできない指揮者は、私は好きになれない。"After all, Rattle is Rattle."😌
…しかし、初稿ならではの多彩な「楽器の滿漢全席」を、視覚含めて楽しむにはもってこいの動画である。観て損はない。
(★★★★★)

インゴ・メッツマッハー指揮/ブンデス・ユーゲント管 (2019)
Ingo Metzmacher / Bundesjugendorchester
Ingo Metzmacher / Bundesjugendorchester
available on Digital Concert Hall
ベルリンフィルの会員制サイト、ディジタル・コンサートホールにある映像。こちら。2019年4月29日のライヴ。ブンデス・ユーゲント管(連邦青年オーケストラ)は、事実上ベルリンフィル配下にある青年オケ。1969年に設立され、カラヤンの時代からベルリンフィルの指揮者や奏者が指導に当たっている。団員は10代の若者ばかりのようだ。
閑話休題。クロウ・コール、ボート・ウィスル入りなので初稿版(1922年版)だ。…殆どが若者だが、かなり年配の人たちも混じっている。アルトフルート奏者は明らかに50代以上だし、サイレンを回す人(電子サイレンでなく手動式を使っている)やクロウ・コールを吹く人も皆ベテラン勢だ。青年オケにベテランが混じって増強してる感じだね。きちんとメリハリがついており、必要最小限の味付けが為されている。…しかしラトルもメッツマッハーも、終結部は全く音を伸ばしてないな…。…本演奏はラトルよりはだいぶマシだが、五十歩百歩と言わざるを得まい。
(★★★★)

ペーテル・エトヴェシュ指揮/ベルリンフィル (2019)
Péter Eötvös / Berliner Philharmoniker
Péter Eötvös / Berliner Philharmoniker
available on Digital Concert Hall
ベルリンフィルの会員制サイト、ディジタル・コンサートホールにある映像。こちら。2019年9月8日のライヴ。初稿版の1997年改訂版(チョウ・ウェンチョン版)を使用している。…曲紹介の文章が「1920年代のニューヨークの喧騒が描かれています」としかなく、不正解ではないが、それだけじゃないんだけどね…。まあいっか。😅
閑話休題。…エトヴェシュの指揮ぶりは、メリハリがある。デュナーミクやフレージングへの細やかな気遣いがある。テンポの緩急や、強調すべき箇所、音を伸ばすべき箇所、スタッカートで音を切るべき箇所への的確な指示。「指揮者としての当たり前の演出」を、きちんとやれてます。…エトヴェシュは本業は作曲家であり、流石にこうした「作曲家がどう演奏してくれとスコア上に書き残しているのか」を掴む能力は長けているはず。…ただやっぱり、ディジタル・コンサートホールは音質がイマイチ…。マイクから遠いし(ステージ上に筍みたいなマイクが生えてない。天井からの吊り下げマイクだけで収録してますよね。…それじゃあやっぱり楽器の力強い音は収録できないはずで…。)、これはやっぱりノーマライザーをかけてるかも知れない。また、サイレンの音がやはり非常に甲高いもので、余り宜しくない。(因みにサイレンはアルミケース型の電子サイレン。…その電子サイレン、ヴァレーズの意図にそぐわない楽器なんじゃ…。手回し式のヘヴィなタイプの方がいいと思いますが…。)終結部のフェルマータはソコソコ、といった感じ。5秒くらいは伸ばしている。…いやでももっと、メチャクチャ伸ばさないと、ソコは。ね。
…まあラトルよりはマシだけど、これより良い演奏はいくらでもあるので、この点数。
(★★★★☆)